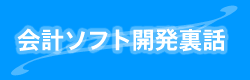« 第3回 経理入門 仕訳 | メイン | 第5回 経理入門 決算書 »
2005年08月15日
第4回 経理入門 元帳
前回は、お金の動きの記録=仕訳の基本について説明しました。
では、この仕訳が積み重なるとどうなっていくのでしょうか。
簡単な例をあげて考えてみましょう。
1月1日(期首)に現金が10万円ありました。
銀行から、現金20万円を借り、手持ちの現金は30万円になりました。
商品を15万円で仕入れ、25万円で売りました。
銀行に10万円返しました。
これらの取引の仕訳(お金の動きの記録)は次のようになります。
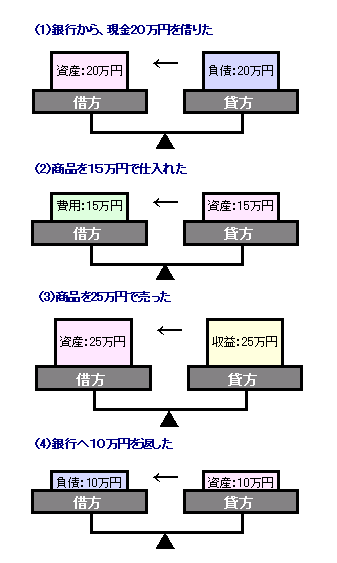
この仕訳(お金の動きの記録)を積み重ねたのが次の図です。
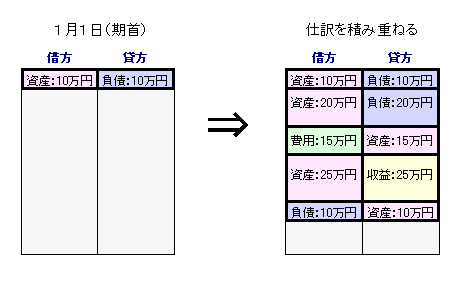
ここで、資産に注目してみましょう。これにより資産の動きがわかります。
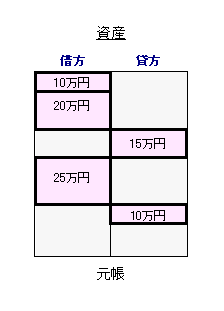
このようにまとめた帳簿を元帳と言います。
実際には、仕訳に記載されている、日付、天秤の反対側(相手科目)、摘要も記載されます。つまり、元帳は仕訳の抜粋と言い換えることもできます。
資産の元帳の代表的なものに、よくご存知の現金出納帳や銀行口座の通帳などがあります。
さらに、この元帳の借方と貸方をそれぞれ合計し、借方から貸方を引くと残高を知ることができます。
なぜ、借方から貸方を引くかと言えば、資産は借方に配置されているので、借方に残高が出るようにするためです。
この例では、最初に10万円持っていて、20万円借りて30万円となり、15万円で仕入をして15万円残り、25万円で売って40万円となり、10万円返して最終的に手元の現金は30万円となりました。
図の残高の30万円と一致してますね。
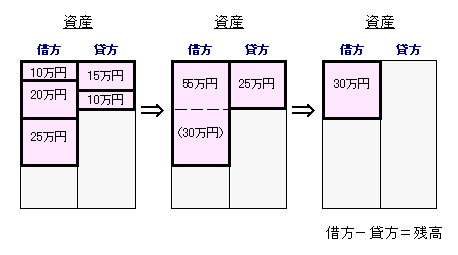
同様に、負債、費用、収益の元帳と残高(合計)も図にしてみました(下図)。
ここで、費用と収益の借方と貸方の差が残高ではなく合計となっているのは、費用と収益は期首にリセットされ、残高という概念がないためです。
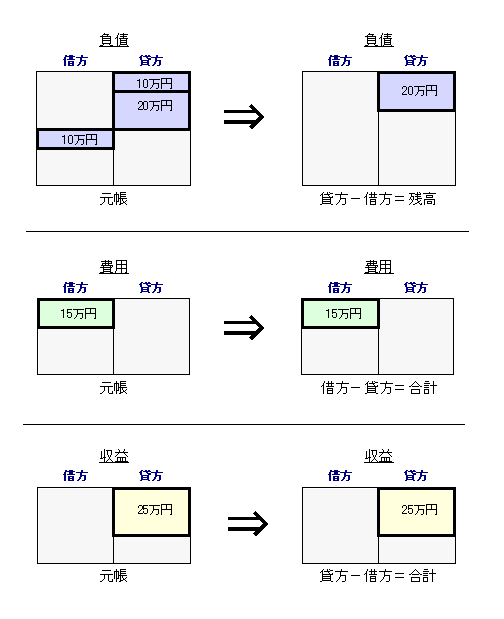
この図を見ていただいてもわかるように、通常の取引では費用は借方と決まっているため、借方と貸方の差を計算するまでもなく、借方の合計が、そのまま合計となります。そこで、貸方欄を省略して、仕入帳や経費帳として帳簿を作成することも多いです。
同様に、収益では、借方欄を省略して、売上帳を作成します。
簿記は、帳簿の種類が多くて難しいと感じる方もいらっしゃると思いますが、以上のことからわかるように、売上帳も仕入帳も経費帳も、全て元帳のアレンジバージョンなのです。ここでは触れませんが売掛帳や買掛帳もそうです。
さて、仕訳を積み重ねて、機械的に分類すると元帳が作成され、残高(合計)が計算されるということがわかりました。
この残高(合計)を集計したものが決算書となっていくわけですが、これについては次回としたいと思います。
投稿者 IJssel : 2005年08月15日 10:00
コメント
元帳の説明は判りやすかったです。
投稿者 江森和男 : 2005年10月16日 10:24